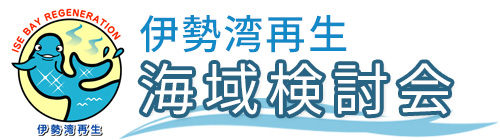MENU
【開催結果】伊勢湾・三河湾の水産資源に必要な栄養や生息場について考えるシンポジウム(第2回)を開催しました!
2024年10月23日
水産資源の回復に向けた栄養塩の管理や藻場・干潟の生物生息場の環境など伊勢湾・三河湾の再生について考えるシンポジウムを開催し、約200名の皆様にご参加いただきました。
日時
令和6年10月15日(火) 14:00~17:00
会場
名古屋港ポートビル(愛知県名古屋市港区港町1番9号)
内容
1)開会挨拶
愛知県農業水産局長 今田 幹雄
| 水産資源の現状について課題と捉えている。愛知県としても対策として干潟・浅場の造成を行っており、その際に中部地方整備局から造成材の提供を受けていることを紹介した。 |
2)主催者挨拶
中部地方整備局副局長 西尾 保之
| 現在、伊勢湾・三河湾が抱えている水産資源の減少やノリの色落ちなどの課題について言及し、その課題を解決するため、浅場・干潟の造成や伊勢湾シミュレーターによる栄養塩管理とアサリ資源量の関係の予測検討などを行っていることを紹介した。 |
3)来賓挨拶
愛知県漁業協同組合連合会 副会長理事 黒田 勝春
| 近年、海産物の漁獲量は低下しており、原因は栄養塩不足だと考えている。愛知県でも栄養塩の管理運転を行っており、引き続き実施することを希望している。また、このようなシンポジウムが開催されることはありがたく、今後施策に反映され、実りのあるものになることを祈念している。 |
4)基調講演
名城大学大学院総合学術研究科 特任教授 中田 喜三郎
| 高度成長期の沿岸開発に伴い悪化した水質の改善効果を検証するため、伊勢湾シミュレーターを開発した。伊勢湾シミュレーターでは、全窒素や全リン、クロロフィルaの再現性や底層DO(溶存酸素)、アサリ資源量、漁獲量の再現性を確認した。 伊勢湾再生のための栄養塩管理運転と浅場造成におけるアサリ資源量についてシミュレーションを行った結果、浅場造成施策は、餌料不足の環境下ではその効果が発現されない可能性があり、栄養塩管理の施策と組み合わせて実施することで効果が高くなることが示唆される。 『伊勢湾シミュレーターの研究成果について(発表概要)』 |
5)取組紹介
日本福祉大学国際学部 特任教授 千頭 聡
| 伊勢湾再生に関する情報発信に取り組むとともに、市民から見たより良い伊勢湾づくりを検討・提案できるような「理解醸成の場」づくりが重要である。特に、普段海を意識していない方が多いことが課題であり、各種活動において継続的にPRを行うことが重要である。活動の場ではアンケート調査を行い、来場者の環境問題への認知度や再生活動参加への意欲について、概ね同様の傾向が得られた。 今後も地道に活動を行っていくことが重要である。 『伊勢湾・三河湾におけるー持続的な海域環境再生に向けた市民の取組ー』 |
愛知県農業水産局 水産課長 柴田 晋作
| 伊勢湾・三河湾での栄養塩不足に対する愛知県の取組の1つとして、漁業生産に必要な栄養塩管理のあり方を検討するため「愛知県栄養塩管理検討会議」を設置している。本会議では、これまで行ってきた栄養塩管理の社会実験結果を踏まえて今後の対応を検討しており、今後は栄養塩管理の恒久的実施の枠組み作りが必要という提案を行っている。 『愛知県の漁場の生産力強化への取組ー栄養塩管理運転の経過を中心にー』 |
6)話題提供
日本製鉄株式会社 上席主幹 田崎 智晶
| ブルーインフラの取組として、師崎漁協と共同で藻場造成試験(師崎漁協地先)を実施した。港湾整備で発生した浚渫土を、製鉄過程で発生する製鉄スラグと高炉スラグ微粉末と混合し、製造・設置した。3年間の調査結果から、天然石の代替として浚渫土人工石を用いた藻場造成の特徴や可能性が示された。 さらに、野間漁協と共同でノリ施肥試験(野間漁協地先)を実施した。ノリ網の傍に窒素・リン・鉄を供給するユニットを設置した結果、この3栄養素を同時に添加することが有効であることが確認された。 『リサイクル材(鉄鋼スラグ製品)を用いたブルーインフラの取組紹介』 |
NPO法人SEA藻 プロジェクトリーダー 鈴木 望海
| 三重県南部では以前より磯焼けが確認されており、その対策としてガンガゼ類の駆除を行うことで藻場を再生する活動を行っている。三河湾内の西尾市佐久島、蒲郡市などで行っている保全・再生活動の支援も行っており、佐久島では児童生徒が主体となりアマモを増やす取組を継続的に実施、蒲郡市ではアマモを増やす取組や干潟の保全活動を継続的に実施している。 また、再生した藻場等が、Jブルークレジット®として認証・取引され、地域活動のPRや活動の資金が得られるよう、現在、熊野灘地域、佐久島、蒲郡の認証に向けて進行中。 『伊勢湾・三河湾における藻場造成とJブルークレジット®の認証について』 |
7)パネルディスカッション
コーディネーター:青木 伸一 大阪大学大学院工学研究科 名誉教授
パネリスト :千頭 聡 日本福祉大学国際学部 特任教授
鈴木 輝明 名城大学大学院総合学術研究科 特任教授
倉島 彰 三重大学生物資源学科 教授
永田 桂子 NPOシーブリーズ 代表
| 各パネリストより、ご自身の取組について簡単にご紹介いただいた後、ディスカッションを行った。会場の皆様からの意見も交えた議論となり、栄養塩管理の問題についてはすぐにでも対策して欲しいといったご意見もあった。 |