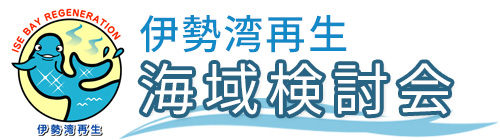MENU
【開催結果】伊勢湾・三河湾の水産資源に必要な栄養や生息場について考えるシンポジウムを開催しました!
2022年10月26日
水産資源の回復に向けた栄養塩の在り方や生物生息場の環境など伊勢湾・三河湾について考えるシンポジウムを開催しました。
日時
令和4年10月25日(火) 14:00~17:00
会場
名古屋市ウィンクあいち(愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
※オンラインによる一般参加
内容
1)開会挨拶
愛知県農業水産局長 矢野 浩二
| 本件の水産業を取り巻く状況は非常に厳しく、近年では伊勢湾・三河湾における栄養塩の減少などによる漁業生産力の低下が大きな問題になっている。愛知県としては、栄養塩の減少に対して、今年度から2年間、矢作川および豊川浄化センターにおいて窒素とリンの濃度を増加して放流する社会実験を行い、効果の検証や漁業生産に必要な栄養塩管理の在り方を検討している。 関係者がこの問題について共通認識を図ることが、今後の取組を進めていくに当たって極めて重要であると考えている。 |
2)主催者挨拶
中部地方整備局副局長 佐々木 淑充
| 沿岸域の開発等によって良好な生物の生息場・生育空間が減少していること、あるいは窒素やリン等の栄養が不足していることで、アサリ等の水産資源の減少やノリの色落ちが問題になっている。中部地方整備局としては、「人と森、川、海の連携により、健全で活力ある伊勢湾を再生し、次世代に継承する」をスローガンに、伊勢湾再生に向けて取り組んでいるが、一朝一夕に答えの出るものではなく地道な努力が必要と考えている。 本シンポジウムでは、これまでのきれいな伊勢湾から豊かな伊勢湾を目指し、皆様と一緒に考えていきたい。 |
3)来賓挨拶
愛知県漁業協同組合連合会 代表理事会長 山下 三千男
| 近年では、イカナゴやアナゴなどの魚類やアサリなど貝類の大幅な減少、また、ノリ、ワカメなどの海藻類も生育不足で生産量は著しく減少し、愛知県水産業の存続に関わる深刻な問題となっている。その最大の要因として、伊勢湾・三河湾における栄養塩不足があると漁業者は考えている。関係者がこの問題について認識を共有することが、解決に向けて重要であると考えている。 本シンポジウムの内容が、国、県の施策に反映され、実りあるものとなるよう心から期待している。 |
4)基調講演
名城大学大学院総合学術研究科 特任教授 中田 喜三郎
| 「豊饒な宝の海を取り戻す」を目標に、どのようなことをすれば貧酸素水塊を抑制できるのか、生物資源量が回復するのかといった対策を検討するため、伊勢湾シミュレーターの開発が始まった。 様々な検討を重ねた現状のシミュレーターにおいて、伊勢湾・三河湾の水質環境およびアサリ資源量の再現計算を行い、窒素、リン、クロロフィルaの変化を概ね再現できた。しかし、アサリ資源量と実際の漁獲量を対比したところ、資源量の低下が漁獲量の低下を追従できていないところが一部あり、アサリの肥満度が低下した際の資源変動の再現に課題が残っている可能性があると推測された。 伊勢湾・三河湾沿岸に位置する27か所の下水処理場施設における管理運転を想定した予測計算を行った。現状の規制値の範囲内で実施できる上限とした管理運転で、アサリ資源や動物プランクトン量(魚類資源に繋がる)が明瞭に回復する状況が予測された。 |
5)話題提供
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 理事長 桑江 朝比呂
| 地球温暖化を抑制するためには、大気中の二酸化炭素を減らす必要がある。排出を減らすだけでなく、大気からのCO2をほかの場所へ持っていくことも必要。日本は今、毎年11.5億トンのCO2を排出しており、90%削減したとしても1億トン以上の残余排出が残る計算になる。どうしても減らせない残余排出をゼロにする方法として、ブルーカーボンというのは非常に重要な役割を担う技術になるだろうと、この1年間特に着目されている。ブルーカーボンの本質は数千年の時間で炭素がたまることで、これが非常に重要。少なくとも国内では、藻場が吸収源として重要な役割を担っているといった現状を受けて、増やしていくことができればいいと思うが、地元漁業者やNPOの皆様のボランティア的な活動によって支えられている部分があり、取組が進まない。こういった活動を進めていくためには、具体的な活動の成果を数値や経済価値で示すことが必要と考え「ジャパンブルーエコノミー技術研究組合」を設立し「Jブルークレジット」というものを作った。「Jブルークレジット」は、地元で藻場等の回復活動を行っている方の活動資金や人材不足の悩みと、民間企業等の資金はあるけれど直接自分たちがCO2の吸収や削減ができないといった悩みを交換し合いwin-winの関係になるシステム。このようなシステムが将来必要になると考え、今、社会実験的に「Jブルークレジット制度」というものをやっている。ぜひご関心のある方は少し工夫をしていただければ、このクレジット制度を活用していただける可能性がある。 |
愛知県水産試験場 主任研究員 曽根 亮太
| 伊勢湾において窒素やリン、クロロフィルは減少傾向を示しており、2010年以降は基礎生産力や植物プランクトンの増える力が低下している現状にある。シャコやアナゴの資源変動要因で最も重要で有名なのはやはり貧酸素水塊の存在にある。伊勢湾・三河湾に夏を中心に広く分布し、直接的に生物のへい死をもたらすだけでなく、生物の逃避によって、その貧酸素水塊の縁辺部に生物が固まることで小さい魚も含めて取れてしまい、それを放流しても死んでしまうといった貧酸素水塊に付随する問題もある。今、伊勢湾・三河湾では基礎生産力の低下が起きており、その変化に対応するように内湾の生態系も変化していることが考えられる。 |
6)パネルディスカッション
コーディネーター:中田 喜三郎 名城大学大学院総合学術研究科 特任教授
パネリスト :鈴木 輝明 名城大学大学院総合学術研究科 特任教授
青木 伸一 大阪大学大学院工学研究科 教授
桑江 朝比呂 ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 理事長
蒲原 聡 愛知県水産試験場 場長
| 各パネリストより、これまで伊勢湾やその海域で取り組まれてきた実績や活動内容を簡単にご紹介いただいた後、ディスカッションを行い、会場の皆様からのご意見も交えた議論となった。栄養塩不足による水産資源の品質の低下と、それによる価格の低下により、生産者が減少していることを危惧しているといったご意見があった。 その他に栄養塩の管理についての社会実験をしっかりと行い、評価し効果があることを示すということ、さらには類型指定の見直しについても前向きに検討していく必要があるといったご意見もあった。 |
参考資料
『次第「伊勢湾・三河湾の水産資源に必要な栄養や生息場について考えるシンポジウム」』
『リーフレットA3 (令和3年度_海域検討会_研究WGまとめ)』