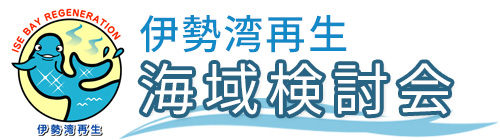MENU
【開催結果】伊勢湾の栄養管理と水産資源における気候変動対策について考えるシンポジウムを開催しました!
2023年9月28日
水産資源の回復に向けた栄養塩の在り方やブルーカーボンを活用した気候変動対策について考えるシンポジウムを開催し、約200名の皆様にご参加いただきました。
日時
令和5年9月27日(水) 14:00~17:00
会場
ホテル津センターパレス(三重県津市大門7-15)
内容
1)主催者挨拶
中部地方整備局副局長 西尾 保之
| これまで陸域から伊勢湾に流入する汚濁負荷の削減に積極的に取り組んできた結果、伊勢湾流域からの流入負荷量が減少し、水質が改善する傾向にある一方で、アサリ等の水産資源の減少やノリの色落ち等が課題になっている。このような課題に対して、中部地方整備局では「人と森・川・海の連携により健全で活力ある伊勢湾を再生し、次世代に継承する」ことをスローガンに伊勢湾再生に向けた取り組みを推進している。「豊かな」伊勢湾を目指し、水産資源の回復に向けた栄養塩の在り方やブルーカーボンを活用した気候変動対策について、皆様と共に取り組んでいきたいと考えている。 |
2)来賓挨拶
三重県漁業協同組合連合会 代表理事会長 濱口 慶太
| 禁漁久しく復活の兆しが見えないコウナゴ、水揚量の低迷が続くアサリなどの二枚貝や色落ちに悩まされるノリ養殖と、伊勢湾の漁業は厳しい状況が続いている。今一度、伊勢湾のおかれる状況を見つめ直し、伊勢湾の将来について共に考える機会としたい。食糧の確保においても、漁業はますます重要な役割を果たさなければならない。本日出席されている関係者の皆様、漁業者の皆様には引き続きのご支援、ご協力を賜りたい。 |
3)基調講演
ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 理事長 桑江 朝比呂
| 2050年カーボンニュートラルの達成に向けて、CO2排出削減に加えて、どうしても出てしまう排出を吸収・除去する必要がある。その技術の1つとしてブルーカーボンあるいは藻場を活用した生態系の保全、再生というものがある。従来の研究結果において、世界レベルでは内湾はCO2放出の傾向がある一方で、日本、特に三大湾(伊勢湾・東京湾・大阪湾)では、通年で吸収の傾向を示す。この要因の有力な候補は、下水処理水と考えられている(現在も研究中)。そのため、下水処理という人工的なシステムと藻場・干潟といった自然のシステムを組み合わせることで、より効果的なCO2除去や藻場・干潟といった環境再生も可能となる見込みがある。 |
4)話題提供
三重県環境生活部大気・水環境課水環境班 係長 小林 紀有起
| 近年、全ての海域において環境面から見たときには窒素・リンの"きれいさ"という観点では状況の改善が見られている。その一方で、クロノリの漁場における溶存態の窒素濃度の低下や伊勢湾内における表層のクロロフィル濃度の低下がみられる。このような背景を踏まえて、きれいさだけでなく豊かさも求めていくことが重要となってきており、栄養塩の管理と藻場の保全・再生ということを両輪で進めていくことが重要と考えられている。 |
鳥羽磯部漁業協同組合 戦略企画室 室長 小野里 伸
| クロノリ全体の生産量は非常に減っている。これには黒潮大蛇行の影響や、高水温、食害などの要因が考えられている。食害に対しては、このような問題があることを魚の食と一緒に伝えていくことが大事だと考えている。また、Jブルークレジット制度の活用によって、ブルーカーボンを増やすために、ノリの生産を増やすことや子どもの将来を考えることを行っていきたい。また、賛同企業との社会共生の取組を行っていきたい。海と海藻を通じて、子どもたちの未来をつくる仕事を一緒にやっていけたらと考えている。 |
5)パネルディスカッション
コーディネーター:青木 伸一 大阪大学 名誉教授
パネリスト :鈴木 輝明 名城大学大学院総合学術研究科 特任教授
松田 浩一 三重大学大学院生物資源学研究科 教授
桑江 朝比呂 ジャパンブルーエコノミー技術研究組合 理事長
小野里 伸 鳥羽磯部漁業協同組合戦略企画室 室長
大野 愛子 鳥羽市海女・フォトグラファー
| 伊勢湾における水産資源回復のきっかけの1つはブルーカーボンかもしれない。ブルーカーボンは、CO2の吸収だけでなく、様々な環境価値、社会的価値を生み出すこともあり、様々なところと連携をしていくというきっかけにもなる。輪を広げていくという意味では非常にメリットがある。 |