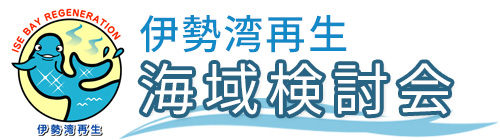【開催結果】「第19回 海の再生全国会議 in 伊勢湾」を開催しました!
海辺の環境再生に取り組む活動団体の情報共有等を目的に「第19回 海の再生全国会議 in 伊勢湾」を開催し、会場とオンラインで約200名の皆様にご参加いただきました。
また、本会議に先立ち、一般財団法人みなと総合研究財団が主催する「第2回 全国海の再生・ブルーインフラ賞 授賞式」を開催しました。
日時
令和7年2月28日(金) 13:00~17:00
会場
中電ホール(愛知県名古屋市東区東新町1番地)
内容
【第2回 全国海の再生・ブルーインフラ賞 授賞式】
詳しくはこちらをご覧ください→〔https://www.wave.or.jp/doc/blueinfra.html〕
1)主催者挨拶
2)表彰
国土交通大臣賞(1取組)
取組名:佐久島の海を守る~子どもたちが主体で行うアマモの保全活動~
応募者:愛知県西尾市立佐久島しおさい学校
みなと総研賞(2取組)
取組名:岩手県洋野町における増殖溝を活用した藻場の創出・保全活動
応募者:岩手県洋野町
取組名:関西国際空港 豊かな藻場環境の創出
応募者:関西エアポート株式会社
3)受賞者による取組内容の報告
4)講評
5)閉会
【第19回 海の再生全国会議 in 伊勢湾】
1)主催者挨拶
中部地方整備局 副局長 西尾 保之
| 海の再生全国会議は、平成18年度から各湾(東京湾、大阪湾、広島湾、伊勢湾)持ち回りで開催しており、伊勢湾での開催は平成30年度に続き今回で4回目となる。本会議がご参加の皆様にとって有意義な会議になること、また、全国の海の再生を後押しするものとなることを祈念している。 |
2)基調講演
名城大学大学院 総合学術研究科 特任教授 中田 喜三郎
| 豊饒(ほうじょう)な宝の海を取り戻すために、伊勢湾再生海域推進プログラムが策定され、高度経済成長期の沿岸開発に伴い悪化した水質の改善効果を検証するため伊勢湾シミュレーターを開発した。伊勢湾シミュレーターでは、窒素やリン、クロロフィルa、底層DO(溶存酸素)、アサリ資源量、漁獲量の再現性を確認し、概ね再現できたものと考えられる。 伊勢湾再生への有効な施策として、栄養塩管理運転と浅場干潟造成の相乗効果や効果的な実施方法・課題等についても検討した。栄養塩管理運転を実施すると、夏季に急激な資源増加が生じ、秋季に向けて肥満度が低下する傾向となるため、この時期に常時運転を行い肥満度低下を防ぐことが以降の資源維持に重要と考えられる。また、浅場造成のみを行った場合、餌料不足の環境下では、その効果が発現されない可能性があり、栄養塩管理の施策と組み合わせて実施する必要が示唆される。 『伊勢湾再生や今日の海洋環境に関わる最新の話題』 |
3)話題提供
三重県環境生活部環境共生局 大気・水環境課 主任 水谷 彼方
| 三重県では、近年のノリの色落ちやアサリ、魚類等の漁獲量減少を受け、令和4年10月に第9次水質総量削減計画を策定した。下水処理場の栄養塩類管理運転がより柔軟に実施できるよう、下水道業の基準値を国が定めた範囲の上限となるよう見直した。現在、公的機関が管理する下水処理場において栄養塩類管理運転の調査と試行を開始しており、検証結果をもとに今後の施策等にフィードバックしていく。管理運転の効果を把握するため、令和4年度から流域下水処理場の周辺海域における水質、植物プランクトン等を調査しており、効果を予測・検証する数値シミュレーションを開発、令和6年度からは解析に着手している。 『三重県における栄養塩類管理の取組』 |
蒲郡市教育委員会 生涯学習課 副主幹 杉浦 崇文
| 蒲郡市では、「三河湾環境チャレンジ(海の環境学習)」を実施している。目的は、地元の海に親しみ生き物と触れ合う機会にすることや、蒲郡の海への興味・関心を深め、海への環境に関する問題意識を醸成することであり、平成17年から開始し、令和6年度では市内全13小学校が実施している。 各学校が実施する水族館見学や教材、海岸散策を通して「海・生き物」への意識を掘り起こすことで、三河湾環境チャレンジへの興味・関心を持つようになる。学校付近の海にて、磯の観察や生き物採取を行い、まとめでは海の生き物図鑑や絵日記、リーフレット等を作成する。さらに、作成した成果物は、蒲郡市生命の海科学館にて「三河湾環境チャレンジ作品展示会」として市内外、県外の大勢の人たちに広く発信している。 『三河湾を支える将来世代の育成』 |
鳥羽磯部漁業協同組合 戦略企画室 室長 小野里 伸
| 鳥羽は「漁業と観光のまち」として漁業と観光業が連携して市の産業を牽引している。鳥羽には豊富な漁業種類が存在しており、重要な海産物のひとつである黒のりは、摘採後、葉体を脱水し氷点下20度で冷凍する「葉体冷凍」を行うことで、独特の旨味が生まれ、消費者からも高い評価を受けている。 近年、ブルーカーボンに着目しておりそのきっかけとして、栄養不足や海水温等による黒のりの色落ちが原因で廃棄処分せざるを得なくなったことがあげられる。令和5年度には、「鳥羽港周辺海域の漁業と観光業連携による海女文化・地域振興に資するBCプロジェクト」としてJブルークレジット®が認証された。 今後も、ブルーカーボンを活用して食育活動や環境保全等を行い、海というフィールドを通じた人と資源の循環を目指していく。 『ブルーカーボンでつながる人と資源の循環』 |
中部国際空港(株) 執行役員 塩田 昌弘
| 中部国際空港では空港護岸において、海域環境に配慮した傾斜堤護岸の採用や岩礁性藻場の創出を行っている。藻場には、魚類等の産卵場や隠れ場となる魚礁効果、酸素放出と栄養塩類の吸収による海水浄化機能、二酸化炭素の吸収による温暖化防止効果があり、緩傾斜護岸にて藻場造成を実施。現在では、多年藻を用いた藻場に、1年藻のアカモクが自然繁殖している。さらに、漁業者をサポートして地域の大学と複数の企業を結びつけた産学連携により、地域資源の更なる可能性の研究に発展し、除菌液を開発。セントレアのターミナル内の手指消毒液として利用している。 『いのち豊かな伊勢湾再生に向けた森づくり』 |
4)各湾からの報告
東京湾(関東地方整備局 港湾空港部)
| 東京湾では、NPOや一般市民等の多様な主体と協働でアマモ場再生に取り組み、人々の海への理解や関心を高める「東京湾UMIプロジェクト~東京湾・海をみんなで愛するプロジェクト~」を実施しており、5月頃に花枝を採取したのち、種子選別、苗床の作成を行い、海底に埋めている。 『豊かな海の再生~東京湾再生活動について~』 |
大阪湾(近畿地方整備局 港湾空港部)
| 大阪湾における『豊かな「魚庭(なにわ)の海」』の取り組みとして、藻場、干潟、浅場、緩傾斜護岸等の整備、維持管理を行っている。また、大阪府万博開催に向けて会場周辺海域にブルーカーボン生態系を創出して大阪湾における取組を国内外に発信。万博開催までに約1000m2の藻場創出を予定している。 『大阪湾からの報告~コアテーマ「豊かな海の再生」について~』 |
広島湾(中国地方整備局 港湾空港部)
| 多様な主体の参画による取組の活性化を図るため、官民連携組織「広島湾さとうみネットワーク」を設置し、行政だけ、民間だけでは実現が困難な取組や、民間のアイデアによる新しい取組を官民が連携して進めている。官民連携組織による取組として、環境学習イベントや清掃イベント、藻場の移植等を行っている。 『豊かな広島湾再生の取り組み紹介』 |
伊勢湾(中部地方整備局 港湾空港部)
| シンポジウムを開催し情報共有を図ることや、環境イベント等への協力、ブース出展によるPR活動等を行っている。環境イベントでは来場者を対象にアンケート調査を実施しており、海との関わりやイベントへの参加等についてお聞きしている。その結果、イベント時の体験工作体験講座の支援が効果的だということ分かり、今年度から新たに「海藻しおり工作体験」を実施し、幅広い年齢層に楽しんでいただけた。 『伊勢湾における取り組み紹介』 |
5)パネルディスカッション
コーディネーター:千頭 聡 日本福祉大学 特任教授
パネリスト :杉浦 崇文 蒲郡市教育委員会 生涯学習課 副主幹
小野里 伸 鳥羽磯部漁業協同組合 戦略企画室 室長
塩田 昌弘 中部国際空港(株) 執行役員
三島 理 国土交通省中部地方整備局 港湾空港部長
| 教育、漁業、企業、行政の視点から「多様な主体の連携」、「将来世代の育成」についてパネルディスカッションを行った。 パネルディスカッションでは、豊饒(ほうじょう)な宝の海を取り戻すことの重要性を多くの人に幅広く知ってもらうためには、海と人とのつながりが見える化することや、学校と家庭と地域のつながりが大切である、という話などがあった。 |